![]()
| ※1 | 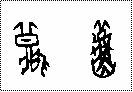 |
※2 | 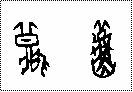 |
実は,「秋」を甲骨文字(※1)ではこのように記されていました。子どもたちにこの甲骨文字を見せると即座に「虫」だと答えます。説文解字という辞書には(※2)の様に記されています。のぎへんがあり,旁(つくり)の部分が上部には亀の様な文字,そして下部には「火」が読めます。
「禾」はまさしく「秋の実りである穀物」を示しています。「亀のような文字」は虫害をなす生き物を表し,その虫たちを火であぶっていぶしだしている様子を示しています。秋という漢字の語源を白川静先生はこのように紹介されています。
秋は頭に次のような語句をつけて表されます。「食欲の秋」「スポーツの秋」「読書の秋」「芸術の秋」があります。
「秋の七草」もあります。このごろはテレビで「ふじばかま」を植えようというキャンペーンがなされています。ちなみに「秋の七草」とは萩(はぎ)尾花(おばな:薄(すすき)のこと)葛(くず)女郎花(おみなえし)藤袴(ふじばかま)桔梗(ききょう)撫子(なでしこ)のことで,春の七草のように粥にして食することはありません。
秋にちなんだことわざと言えば,「天高く馬肥ゆる秋 」「秋風が吹く 」「秋を吹かす 」「一日三秋 」「一日千秋
」「一刻千秋 」「千秋晩成 」「春秋の争い 」「春秋に富む 」「春秋高し 」「物言えば唇寒し秋の風
」「一葉落ちて天下の秋を知る 」などたくさんあります。
小倉百人一首にも秋を詠んだ句が三句あります。
秋の田の かりほの庵の 苫をあらみ わが衣手は 露にぬれつつ
(第1番:天智天皇)
(解釈) 秋,田に実った稲の穂を刈る季節――田の側の掘っ建て小屋は屋根の苫の目が荒いから,私の袖は落ちてくる露でぬれ続けていることだよ。
奥山に 紅葉踏み分け 鳴く鹿の 声聞く時ぞ 秋は悲しき
(第5番:猿丸大夫)
(解釈) 山の奥深くで,積もったもみじを踏み分けて妻を恋い慕って憐れに鳴いている鹿の声を聞くときには,何にもまして秋が悲しく感じられる。
み吉野の 山の秋風 さ夜更けて ふるさと寒く 衣打つなり
(第94番:参議雅経)
(解釈) 吉野の山から冷たい秋風が吹き降ろし,夜も更けて,かつて都であったこの吉野の里は更に寒くなり,砧で衣を打つ音が寒々と聞こえてくることだよ。
三夕(さんせき)と言われる句もあります。三夕とは,下の句が「秋の夕暮れ」で終わる有名な三つの句のことだそうです。
寂しさは その色としも なかりけり 槙立つ山の 秋の夕暮れ
(寂蓮法師)
心なき 身にもあはれは 知られけり 鴫立つ沢の 秋の夕暮れ
(西行法師)
見渡せば 花も紅葉も なかりけり 浦の苫屋の 秋の夕暮れ
(藤原定家)
つれづれに 秋という文字を見つめながら,思い浮かべてみました。秋をゆったりと楽しむ心のゆとりを持ちたいものです。