

平成21年3月4日(水)室町小学校 多目的室Ⅰ
6年生が総合の時間に,「昔の人とごみ」の関係から,考古学について学習しました。
総合地球学研究所の,内山純蔵先生に教えていただきました。
 |
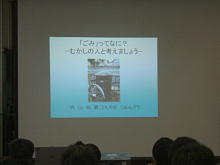 |
 |
| 「考古学」とは,大昔の人が,環境 とどうつき合っていたかを学ぶ学問 です。 |
日本では,ごみ=汚い,役に立たないものとされていますが,フィリピ ンでは,世界各国から集められたごみを処理し,そのごみを売って, 生活している子どもたちが,一万人以上もいるそうです。ごみは,いわ ゆる「宝」とされているのです。 |
|
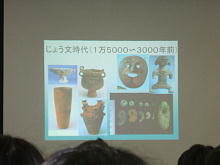 |
 |
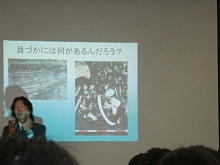 |
| 時代は遡って,縄文時代のくらし について,思い起こしながら,考え ていきました。服や靴もちゃんと はいて生活していたようです。土器 や土偶という物も作られました。 |
「貝塚」とは,いらないものが集め られたゴミ処理場のようなもので す。現代では,ゴミ箱は部屋の片 隅に置かれますが,大昔では,村 や家の近所におかれ,町の中心 におかれました。 |
貝塚には,動物の背骨や食べかす ,木の実などが集められています。 白く残ったものは,貝です。そして, 貝塚には,「死体」も埋められていた のです。それはなぜでしょう? |
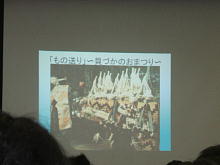 |
 |
 |
| 北海道ではアイヌの人による, 「もの送り」という貝塚のおまつりが あります。貝塚に,物・人・出来 事すべてのものを集めて,神へおく るという習慣があります。「また帰っ てきてね。」という気持ちをこめて, 貝塚に埋められているのです。昔 の人々は,ごみは「神様のもとへ 帰る場所」と考えました。 |
実際に,貝塚から掘られた骨や貝などを先生に,見せていただきました。 右側にあるのは,「オオヤマネコ」の骨です。 「すべての物には,魂がやどっているのだ。」ということを実感できた ようです。 |
|
現代では,邪魔とされている「ごみ」ですが,昔の人々にとっては,「魂」であり,「宝」でした。
今日の学習を通して,物や人を大切にし,より良く生活していこう,ということを
学んだのではないでしょうか。