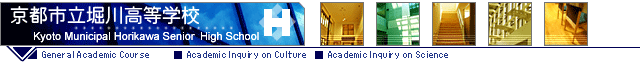 |
||||||
| ■ 過去のSSHの取り組み | ||||||
| 1.専門科目『探究基礎』・『自然探究』を核とした「未来の科学者」養成のための理数系教育環境と 指導法および大学・研究機関との継続的・発展的な連携のあり方に関する研究開発を行う。 1)対象生徒は自然探究科1・2年生(1年生は自然探究科希望生徒)とするが、 研究成果は普通科を含め全生徒に還元する。(「自然科学部」での活動は全生徒を対象とする) 2)『探究基礎』では、メディアリテラシー([受けとる力]・[考える力]・[判断する力] [表現する力])と幅広い言語能力(日本語・英語・数学・コンピュータ)の習得を前提として、 論文作成と資料に基づく発表を到達点としている。体験的な学習を通して、課題解決に至るための、 主体的な課題設定能力を培うことに重点を置く。 3)『自然探究』は、物質・数学・宇宙・地球・生命等をテーマとし、「人間が自然・物質をどの ように理解・把握してきたのか」について実証的に学ぶ自然科学史の学習で、科学者をめざす者 としての素養を身につけるための科目である。 2.研究開発内容 1)専門科目「探究基礎」・「自然探究」を軸とした取り組み ● 自然探究科1年次「探究基礎」における取り組み 「探究基礎」の授業内容をより一層専門化して実施する。
●自然探究科2年次「探究基礎」(2年生6月〜10月)・「自然探究」における取り組み ○「探究基礎」 1年次のグループ研究で習得した方法を基盤に個人研究に発展。 大学での専門研究に向けた個人テーマ設定。 大学・研究機関等の見学・講義・実験のための訪問。 研究レポートの中間発表。 研究成果発表後、優秀論文を論文集にまとめる。(次年度学園祭でも公開) ○「自然探究」 物質・宇宙・生物の進化の流れを中心に科学者として不可欠な素養を習得。 適宜、研究者の特別講義を実施する。 ●理数系科目における取り組み 数学、理科(物理・化学・生物・地学)において、特に「自然探究科」生徒を対象に、 ソフト・ハード両面から学習内容の高度化・深化を図る。 2)「探究基礎」・「自然探究」における大学・研究機関との連携 連携する大学・研究機関は次のとおり。 ○京都大学大学院 理学研究科 ○京都大学大学院 情報学研究科 ○京都大学大学院 人間環境科学研究科 ○京都大学大学院 エネルギー科学研究科 ○京都大学 数理解析研究所 ○京都大学 生態学研究センター ○京都工芸繊維大学 工芸学部 ○大阪大学大学院 理学研究科 ○大阪市立科学館 学芸課 3.フィールドワークの実施 環境への理解や地球規模の視点を養うため、 また科学への理解を深め憧れを持たせるために、 主として1年生を対象に実施する。 平成15年度に実施したフィールドワークは以下のとおり。 ・8月19日〜20日 滋賀県伊吹山夜間登山 (天体観測、高山植物の観察、地質解説) ・10月18日〜20日 飛騨方面合宿 (根尾谷断層記念館/京都大学飛騨天文台/スーパー・カミオカンデを見学、福地化石調査) ・12月13日 宇治田原化石調査    ・「自然科学部」での活動 学校全体に科学的精神を育む場として、自然科学に対する興味関心を深め日常的、 実際的に活動する部活動を創設した。 自然探究科生徒が探究基礎等で学んだ方法を用いて研究を深める機会にもしたい。 (活動分--数理科学班/生物・化学班/宇宙・地球科学班) ・SSHライブラリーの創設 探究基礎・自然探究における指導法の研究や生徒の学習・研究活動の充実に資するため、 本校マルチメディア図書館内に理数系の専門書等を整備する。 ・学術顧問団(運営指導委員会)の創設 SSH指定に伴い、本校教育活動に対して指導助言を受けるため次の各氏に学術顧問 (運営指導委員)を委嘱した。(50音順) 稲盛 豊実 氏(財団法人稲盛財団常務理事) 井村 裕夫 氏(内閣府総合科学技術会議議員) 佐藤 禎一 氏(日本学術振興会理事長) 中坊 公平 氏(中坊公平法律事務所長) 日高 敏隆 氏(国立総合地球環境学研究所長/京都市青少年科学センター所長) 山折 哲雄 氏(国立国際日本文化研究センター所長) ・平成16年度事業経費(申請中) 総額 約15,000,000円 (参考) 人間探究科・自然探究科は、わが国の科学・文化の新たな担い手の育成を目的に設置された専門学科です。 1995(平成7)年8月、京都市立高等学校21世紀構想委員会(教育長の諮問機関。初代会長:河野健二京都大学名誉教授、2代・山田浩之京都大学名誉教授。各界15名の委員で構成)が設置されました。 それから2年余り、1997(平成9)年12月に最終答申を提出するまで真摯な論議が重ねられました。 堀川高等学校の教育改革は、構想委員会設置をさかのぼる1993(平成5)年から校内で主体的に検討してきたものです。それが評価を受け、1996(平成8)年に出された構想委員会第2次答申で堀川高等学校は教育改革のパイロット校に位置づけられ、堀川の取り組みがソフト・ハード両面で具体的に進展することになりました。 第2次答申の中に、次のような文言があります。 ―京都は、守るべきものを見極め、堅持するとともに、そこに新たな展開を生み出してきた。 京都で生まれ育まれた文化は、国内はもとより世界に広がり、京都は、伝統的に、文化・情報を発信する世界の中核であり続けてきた。ノーベル賞を受けた科学者たちが、才能の芽を育成する青年期に京都で学んだことと京都の伝統とは無縁でない。 ―新しい専門学科においては、大学における多様な専門分野に接続することを前提に、生徒の興味・関心、適性、能力に対応して、基礎的研究を行う能力と態度を養うものとする。そのため、新たな堀川高等学校の教育機能を駆使するとともに、大学・研究機関との連携を図り、高度な専門教育にふれる機会を設定する。このことにより、専門研究のための動機づけを行い、主体的な大学進学を実現して後期中等教育から高等教育への円滑な接続を図るものである。 ―新しい専門学科における教育は、教育内容を高度化・深化させることを基軸として多彩な学習内容と学習形態及び学習方法を設定して行うものとする。すなわち、多様かつ高度な学習経験を通して、生徒自身が自己の個性を発見し、自らの進むべき専門分野を主体的に選択する能力を開発する教育である。 議論の中では堀川高校が検討してきた具体的事項が多く取り上げられました。その意味で、答申で提言された内容は堀川が求めるもの、堀川教育の結晶、と言っても過言ではありません。したがって、それらは現在も堀川の取り組みの随所に生かされています。 |
||||||